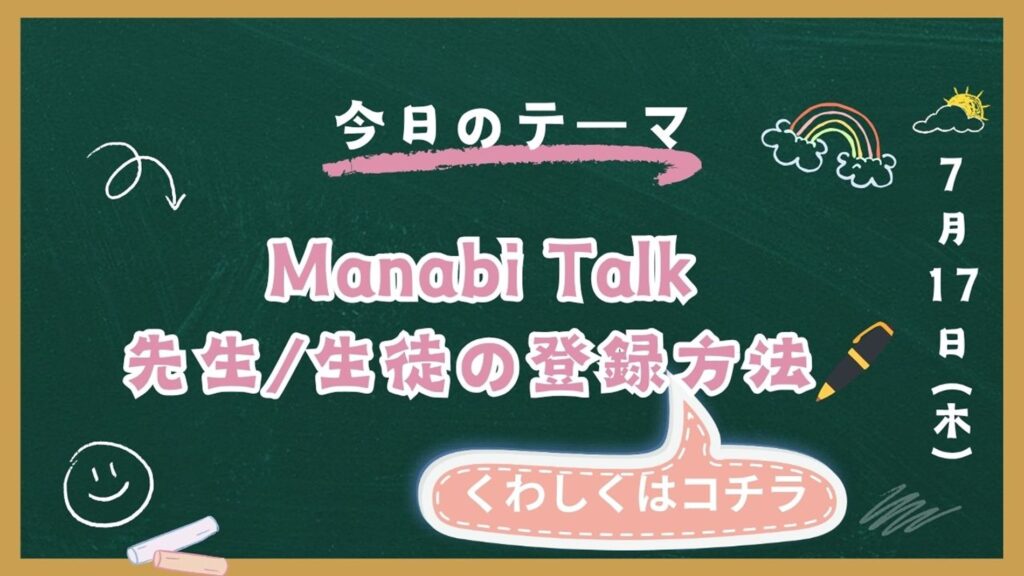学習者の集中力が続かない │オンライン授業で集中力を維持する工夫
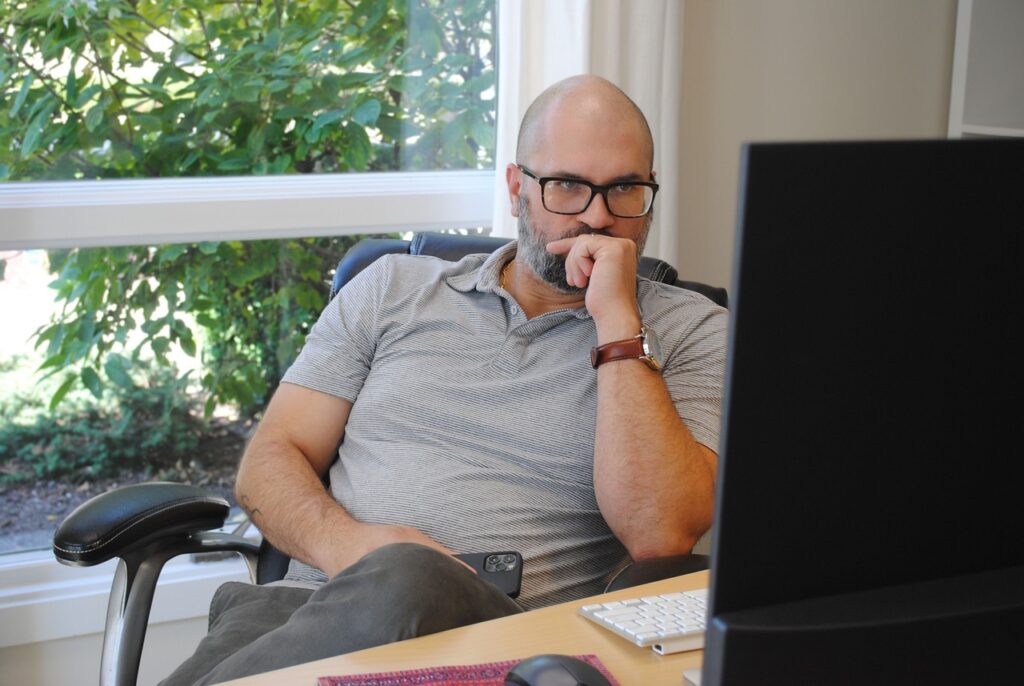
おはようございます。8月27日の水曜日です。今回も引き続き様々なオンライン授業における実例を3回目にみていこうと思います。いつものように今日の元気ワードからスタートをします。
今日の元気ワード~嫌な時には~
私は、軽蔑されても侮辱されても、その立腹をほかに移して他人を辱めることはできない。 福沢諭吉
福沢諭吉の言葉には、人としての誇りと節度が表れています。誰かに侮辱されたり軽んじられたりすると、つい心が乱され、怒りや悔しさをぶつけたくなるものです。
しかし、その感情をそのまま他人に向けてしまえば、自分もまた同じように人を傷つける存在になってしまいます。
大切なのは、受けた屈辱や不快な思いをどう扱うかということ。相手の行為をそのまま鏡のように返すのではなく、自分の中で整理し、冷静に受け止める強さが求められます。
怒りを別の誰かに移すことは、一時的な発散にはなっても、結局は負の連鎖を生むだけです。だからこそ、自分の尊厳を守るとは「仕返しをしない選択」をすることでもあるのです。
他人の態度に自分の行動を支配されず、自分らしい振る舞いを選ぶ――それこそが真の自立であり、品格ある生き方なのだと思います。Have a nice day!!
オンライン授業で集中力を維持する工夫
オンライン授業は場所を問わず学習を可能にする大きな利点があります。しかし同時に、学習者が自宅やカフェなど集中しにくい環境で授業を受けることも多く、集中力を長時間保つのが難しいという課題があります。
授業の途中で学習者がそわそわしたり、画面の向こうで別のことをしている様子が見えてしまったりすると、講師としてもどう関わればよいか迷う場面があるでしょう。
本記事では、学習者の集中力が途切れる原因を具体的に捉えながら、講師ができる工夫や実際の対応事例について紹介します。
授業が単調になり集中が切れる場合
ある中級学習者の授業で、講師が文法解説を続けていると、学習者が少しずつうつろな表情になり、カメラの前で大きなあくびをしてしまったことがありました。
これは講師が一方的に説明を続けたために、学習者が「受け身モード」に入り、注意力が低下した典型的な例です。
このような場面では、解説を短い単位に区切り、その都度「質問してみましょう」「例文を作ってみましょう」と学習者の発話を促すことが効果的です。
特に「自分の生活に関連する例文」を考えてもらうと、学習者は単なる理解にとどまらず、身近なことと結び付けて学べるため集中力が戻ってきます。
講師側も、説明と演習のリズムを意識的に切り替えることで、自然と授業に変化が生まれ、学習者を飽きさせない工夫になります。
そして別のケースを考えてみます。オンライン授業は、対面に比べて周囲の刺激が少なく、同じ画面を見続けることで学習者が飽きやすい特徴があります。そのため、授業の流れに小さな区切りを設けることが効果的です。
例えば、ある講師は25分ごとに「小テストタイム」や「雑談タイム」を設けることで、学習者に集中のリズムをつかませていました。学習者が集中し続けることを前提にするのではなく、自然に意識をリセットできる場を作ることが大切です。
実際に、日本語学習を始めたばかりの社会人の学習者は、業務後に授業を受けることが多く、疲れによる集中力低下が顕著でした。そこで、講師が「この5分は好きな日本の食べ物について話そう」と短いテーマを挟んだところ、学習者は表情を取り戻し、その後の学習にも前向きに取り組めるようになりました。
学習者の生活リズムや環境が影響する場合
ある初級学習者は夜遅くに授業を受けていましたが、仕事の疲れから途中で目が閉じてしまうことがよくありました。また、子どもが隣の部屋で遊んでいる音が気になり、集中できずに画面を見たりそらしたりする様子もありました。
このようなとき講師は、まず学習者の状況を理解することが大切です。
疲れているときに難しい課題を詰め込むのではなく、会話中心に切り替えたり、授業冒頭に軽いアイスブレイクを入れたりすることで気持ちをリフレッシュできます。
また「今日はどのくらい集中できそうですか?」と声をかけ、学習者自身にペースを調整してもらうことも有効です。学習者の生活背景を考慮して柔軟に授業をデザインする姿勢が、集中力の維持につながります。
そして画面に映る情報が単調だと、学習者の集中は途切れがちになります。スライドや教材を画面共有する際には、文字だけでなく画像や短い動画を取り入れることで注意を引き戻せます。
ある大学生学習者との授業では、文法の説明を続けると目が泳ぎ始めました。そこで講師は説明の後に「関連するアニメのワンシーン」を数十秒だけ見せ、「このキャラクターは今、何を言ったでしょう?」と問いかけました。
その瞬間、学習者は笑顔を見せ、答えを考えながら画面にぐっと近づきました。このように、異なる感覚に訴える工夫は、授業全体にメリハリを与え、集中力の持続を助けます。
授業内容が学習者の関心とずれている場合
学習者が興味のない題材に取り組むと、すぐに注意が散漫になってしまうことがあります。
ある上級学習者の例では、教科書の文章を読み進める授業で退屈そうにしていましたが、趣味が日本のアニメであることがわかったため、教材をアニメ関連の記事に置き換えると急に活発に発言するようになりました。
集中力は「面白い」「もっと知りたい」と感じた瞬間に高まります。
講師は学習者の趣味や目標に寄り添った題材を選び、授業に取り入れることが重要です。
例えば、ビジネス日本語を学びたい学習者には実際のメール文や会議表現を題材にする、旅行好きの学習者には観光ブログやレビューを使うなど、関心を引き出す工夫ができます。
興味と授業内容が結びつくことで、学習者は自然と集中した状態を保てるようになります。
そして聞いているだけの授業は集中力を削ぎます。小さな発言機会を頻繁に与えることが、学習者を授業に引き込みます。
例えば、ある主婦の学習者は受け身になる傾向があり、画面越しに黙ってうなずくだけのことが多く見られました。そこで講師は「この単語を使って、今日あった出来事を一文で言ってみてください」と具体的な指示を出しました。
学習者は最初は戸惑いましたが、毎回繰り返すうちに「今日は子どもと公園に行きました」などと積極的に答えるようになりました。
自分の生活に関連する内容を発言すると、学習者自身が「役立つ学び」と感じ、集中力が自然に高まっていきます。
学習者の集中を視覚的・体験的にサポートする場合
オンライン授業では視覚や体験を刺激する工夫も効果的です。ある小学生の学習者は、文字だけの教材ではすぐに注意がそれてしまいました。しかし画面共有でイラストや写真を提示したり、ジェスチャーを交えて単語を説明したりすると、楽しそうに参加を続けられました。
また大人の学習者でも、画面上でクイズ形式を取り入れると、ゲーム感覚で集中を持続させやすくなります。
さらに、授業の途中で短い休憩やストレッチを取り入れることも有効です。「30分ごとに1分間だけ体を動かしましょう」と声をかけると、再びリフレッシュして授業に臨めます。
集中力はずっと持続するものではなく、波があることを前提に、適度に切り替えを設けることが大切です。
集中力の途切れは、必ずしも単なる疲労だけでなく、緊張や不安から生まれることもあります。
あるビジネスマンの学習者は、オンライン会議に慣れているはずなのに、授業中になると急に沈黙する時間が増えました。
講師が「今日はお仕事が忙しかったですか?」と一言添えると、学習者は「はい、頭がいっぱいで…」と打ち明けました。
講師はその後、難しい説明を一時中断し、簡単なゲーム形式の会話練習に切り替えました。
学習者の表情は徐々に柔らぎ、再び授業に集中できるようになったのです。このように、相手の状態を察して柔軟に対応することは、単なる学習効率の向上だけでなく、信頼関係の構築にもつながります。
事前登録を受付中!Manabi Talkについて
集中力を保つ授業を実現するためには、講師と学習者の相互理解と工夫が欠かせません。
Manabi Talkでは、国内運営ならではの安心感と柔軟な仕組みにより、学習者と講師が自分に合ったスタイルで授業を組み立てることができます。
教材の共有や授業時間の調整もしやすく、学習者の関心や状況に合わせた個別対応が可能です。授業が単調にならない工夫や、学習者が安心して学び続けられるように、集中力を長く維持できる環境を整える事も大切です。
オンライン学習における「集中できない」という悩みを解消し、一人ひとりに寄り添った学びを実現する場として、ぜひManabi Talkを活用してみてください。
Manabi Talkは、オンラインで日本語を教えたい講師と、学びたい外国人学習者をつなぐ新しいプラットフォームです。初めて授業を行う新人講師でも、安心してスタートできるよう、教案テンプレートやフォロー体制を整えています。
「これから日本語教師として実践を重ねたい」「でもいきなり大きな現場は不安…」という方にとって、Manabi Talkは実力を磨くための第一歩になるかもしれません。
現在、Manabi Talkではユーザー登録および講師登録を受付中です。ぜひこの機会に、あなたも新たな挑戦を始めてみませんか?
Manabi-talk LP:https://manabi-talk.net/lp

まとめ
在宅で働けるオンライン授業は、日本語教師にとって新しい収入の道を開くチャンスです。
これからは、「教室」だけでなく、「自宅」も立派な教える場となる時代。
ぜひ、オンラインで活躍する日本語教師もお考え下さい!オンライン講師への本登録は8月下旬より可能となります。
それまでのプレ登録をして頂ける方を募集しております。講師様お一人お一人に管理画面をご利用いただけます。8/29に管理画面の共有及び、正式なサイトのオープン日として決定しました。すでにご登録済みの講師様方には改めて、管理画面のURLと利用方法に関する資料をお送り致します。