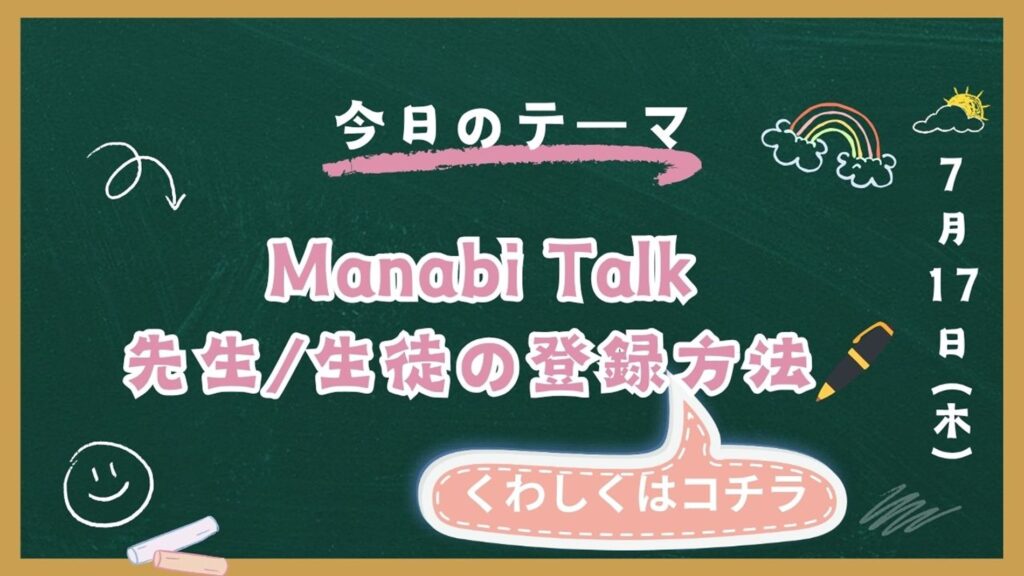学習者がカメラをオフ ― カメラを使わない学習者との効果的な授業運営法について

おはようございます。8月25日の月曜日です。
先日にて「げんき」教材Iの教案例の投稿が終了をしました。今回からは様々なオンライン授業における実例を15回にわけてみていこうと思います。いつものように今日の元気ワードからスタートをします。
今日の元気ワード~前向きに生きると得がついてくる~
「悲観主義者はあらゆる機会のなかに問題を見出す。 楽観主義者はあらゆる問題のなかに機会を見出す。 ウィンストン・チャーチル」
チャーチルの言葉は、物事の捉え方ひとつで人生の見え方が大きく変わることを教えてくれます。
悲観的な人は、せっかくのチャンスに出会っても「ここにはリスクがある」「失敗するかもしれない」と問題ばかりに目がいきます。その結果、一歩踏み出せずに機会を逃してしまうのです。
一方で楽観的な人は、困難や課題に直面したときでさえ「この中に新しい可能性がある」「ここから学べることがある」と前向きに捉えます。
同じ状況でも、どこに焦点を当てるかで未来は大きく変わるのです。もちろん、問題点を無視するのは危険ですが、それを恐れて何も動かないことの方がもっと大きな損失になります。
大切なのは、困難をチャンスに変える視点を持つこと。目の前の壁を「行き止まり」と見るか、「新しい扉」と見るかが、人生の分かれ道になるのだと思います。Have a good day!!
原則、オンライン授業はカメラを通じて行うが
オンライン授業が一般的になった今、多くの日本語教師が経験する悩みのひとつに「学習者がカメラをオフにしたがる」問題があります。
教室であれば顔を見ながら指導できるのに、画面越しでは相手の表情が見えず、反応もわかりにくい。ときには「聞いているのか」「理解できているのか」と不安になることもあるでしょう。
一方で、学習者には学習者なりの理由があり、単純に「オンにしてください」と求めるだけでは解決しません。本記事では、実際の授業場面を想定しながら、この問題にどう向き合えばよいのかを考えていきます。
カメラをオフにする学習者の心理背景
ある日、大学生の学習者Aさんは最初からカメラをオフにして授業に入りました。理由を尋ねると「寮の部屋が散らかっていて恥ずかしい」と小声で答えてくれました。
別の社会人学習者Bさんは「仕事の合間に受けているので、職場の背景を映したくない」と言っていました。
またCさんは単純に「顔を見られるのが苦手」という性格的な問題を抱えていました。
このようにカメラをオフにする背景は多様であり、決して「やる気がない」からではありません。むしろ学習意欲は高いのに、心理的・環境的要因でカメラを使えないケースが大半です。教師がその背景を理解するだけで、対応の仕方が大きく変わります。
学習者がカメラをオフにするのには、それぞれの事情があります。
ある学習者は、自宅の背景が生活感にあふれており見せるのが恥ずかしいという理由を打ち明けました。別の学習者は、朝早い授業でまだ身支度が整っていないことが多いため、カメラをつけることに抵抗を感じていました。
また、IT環境が整っていない学習者は、カメラをオンにすると通信が不安定になるため、仕方なくオフにしているという場合もありました。
こうした背景を理解せずに「カメラをオンにしてください」と強制してしまうと、学習者にプレッシャーを与えてしまい、結果として継続学習の意欲を下げてしまう可能性があります。
授業の冒頭で「今日はカメラをオフでも大丈夫ですよ。ただ、必要に応じてオンにしてもらえると助かります」と柔軟に声をかけることで、安心感を与えながらも対話のバランスを取ることができます。
リアクションが見えない授業の難しさ
学習者がカメラをオフにしていると、こちらの冗談に笑ってくれたかどうか、説明を理解できたのかどうかがわからず、教師側にストレスがたまることがあります。
ある講師は、学習者が黙って頷いていると思ったら、実は途中でネットが切れていたという経験を話してくれました。逆に、全く反応がないため「もしかして聞いていないのでは」と不安になり、授業が一方通行になってしまった例もあります。
このような状況では、教師が積極的に「声での反応」を引き出す必要があります。
たとえば説明のあとに「ここまで大丈夫ですか」と問いかけ、必ず一言返してもらうようにする。あるいは理解を確認するために簡単なクイズを挟むなど、反応を「声」や「チャット」に切り替えて授業を進めることが効果的です。
ある授業では、教師が説明した内容に対して「理解できていますか?」と聞いても沈黙が続き、反応が掴めないことがありました。そのとき、チャット機能を積極的に活用し、絵文字や短いフレーズで返答してもらうよう促したところ、学習者は次第に反応しやすくなりました。
また、スライドや共有資料を色や図を多用して分かりやすく作成しておくと、視覚的な情報が学習者を支えます。
例えば「~すぎる」の文法を導入するときに、「ケーキを食べすぎる → おなかが痛い」のようにイラストを添えたスライドを提示することで、表情が見えなくても理解を促進できます。
音声だけのやり取りになっても、教材が「視覚の代わり」として学習者を助けるのです。
音声表現を中心にした練習方法
カメラがオフであっても、音声を通じたやり取りは十分に可能です。ある中級レベルの学習者は「話すのは好きだけれど、自分の表情を見られるのが苦手」と話していました。
その場合、教師はペアワーク形式を工夫して取り入れ、「電話で会話しているように練習してみましょう」と伝えました。
例えば「~たほうがいいです」を練習する際に、教師が「頭が痛いんです」と話すと、学習者が「病院に行ったほうがいいですよ」と答える、といった電話相談のようなロールプレイを行います。
表情が見えなくても、音声だけで成立するやり取りを中心に設計することで、学習者も安心して練習に取り組めます。むしろ、音声に集中できるため、発音やイントネーションが以前より向上するケースも見られました。
カメラをオフにしている学習者に対して、ある講師は「アイスブレイクで音声だけの自己紹介ゲーム」を取り入れていました。顔は見えなくても、声の抑揚や言葉選びで相手の個性が感じられるため、思った以上にクラスが盛り上がったといいます。
また別の講師は、画面共有をフル活用していました。スライドやホワイトボード機能を使い、学習者に「マウスで丸をつける」「チャットに答えを書く」などのアクションを促すことで、顔が見えなくても「一緒に学んでいる」感覚を作り出すのです。
さらに「今日は顔を見られない分、声をしっかり聞き取りますね」とあえて前向きに伝えることで、学習者も安心し、結果的に発話量が増えたという報告もありました。
適度にカメラオンを促す工夫
もちろん、可能であれば学習者にカメラをオンにしてもらう方が授業はスムーズになります。
そこで効果的なのは「強制ではなく提案」です。ある高校生の学習者は、最初は絶対にカメラをオンにしなかったのですが、教師が「今日は10分だけオンにして、発音練習を一緒にやってみませんか」と提案したところ、徐々に慣れていきました。
また別の学習者は、背景を気にしていたため「バーチャル背景の使い方」を事前に教えると安心してオンにできるようになりました。
大切なのは「あなたの学びをもっと良くするために」という姿勢を示すことです。
オンにしたほうが発音指導や口の動きの確認に役立つことを具体的に説明すると、納得して協力してくれる学習者も増えていきます。
完全にカメラを使わないまま進めるのではなく、授業の中で自然にオンに切り替える瞬間を設けることも効果的です。
ある授業では「好きな食べ物を見せ合いましょう」という課題を設定し、学習者に実際の食べ物や写真をカメラに映してもらう活動を行いました。
このときは、普段カメラをオフにしていた学習者も、自慢の手料理を見せたい気持ちが勝り、積極的に参加してくれました。
また、ゲーム的な要素を取り入れるのも一案です。「今日の気分をジェスチャーで表してみてください」という短いアクティビティを冒頭に挟むことで、楽しい雰囲気の中で一瞬だけカメラをオンにする習慣ができます。
強制ではなく、学習者自身が「やってみたい」と思える工夫が、次第にカメラ利用への抵抗感を和らげるのです。
事前登録を受付中!Manabi Talkについて
こうしたオンライン授業での課題は、個々の教師が一人で抱える必要はありません。
Manabi Talkは、日本語教師と学習者をつなぐ新しいプラットフォームとして、教師同士が知見を共有し合える環境を大切にしています。実際に「カメラオフ問題」についても、ベテラン教師から新人教師まで多くの体験談や工夫が寄せられており、自分の授業に取り入れるヒントを見つけることができます。
国内運営ならではの安心感と柔軟なシステムで、教師が自由に授業を設計できるのも魅力です。カメラの有無に関わらず、学習者と充実した時間を共有できるよう、Manabi Talkをご活用ください。
Manabi Talkは、オンラインで日本語を教えたい講師と、学びたい外国人学習者をつなぐ新しいプラットフォームです。初めて授業を行う新人講師でも、安心してスタートできるよう、教案テンプレートやフォロー体制を整えています。
「これから日本語教師として実践を重ねたい」「でもいきなり大きな現場は不安…」という方にとって、Manabi Talkは実力を磨くための第一歩になるかもしれません。
現在、Manabi Talkではユーザー登録および講師登録を受付中です。ぜひこの機会に、あなたも新たな挑戦を始めてみませんか?
Manabi-talk LP:https://manabi-talk.net/lp

まとめ
在宅で働けるオンライン授業は、日本語教師にとって新しい収入の道を開くチャンスです。
これからは、「教室」だけでなく、「自宅」も立派な教える場となる時代。
ぜひ、オンラインで活躍する日本語教師もお考え下さい!オンライン講師への本登録は8月下旬より可能となります。
それまでのプレ登録をして頂ける方を募集しております。講師様お一人お一人に管理画面をご利用いただけます。