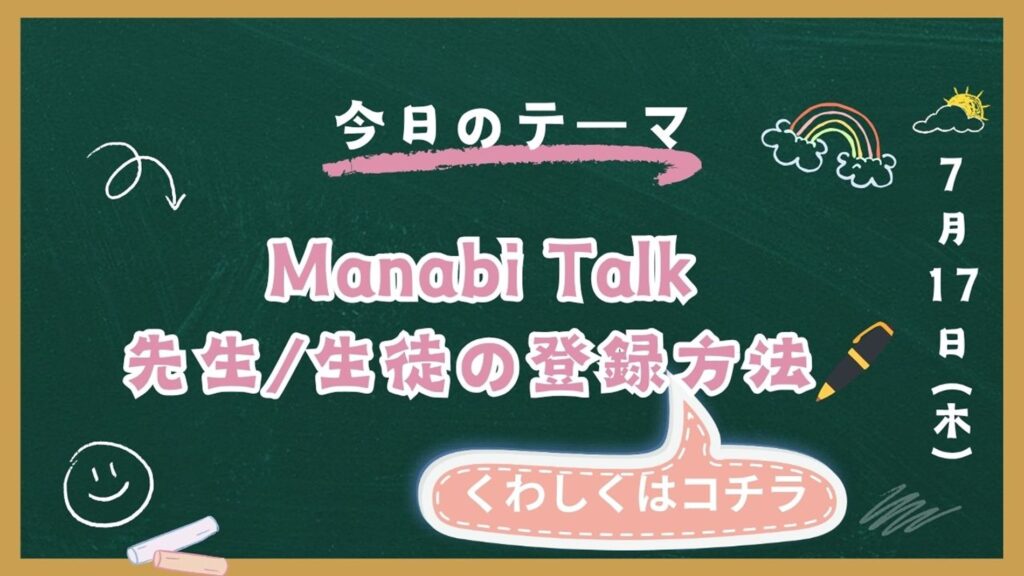げんき第12課「病気」|オンライン授業での展開例と教案
おはようございます。こんにちは。8月22日の金曜日です。今日も昨日に引き続き、げんきの教案例について見ていきたいと思います。本日は第12課「病気」です。それでは、今日の元気ワードからスタート!
今日の元気ワード~~
「私たちは、毎年毎年、違った人間になる。一生同じ人間であるとは思わない。 スティーブン・スピルバーグ」
スピルバーグの言葉は、人の成長や変化の本質を突いています。
私たちは年を重ねるごとに経験を積み、新しい出会いや出来事に触れることで、少しずつ考え方や感じ方が変わっていきます。
昨日まで大切にしていた価値観が、今日には違った形に見えてくることもあるでしょう。そうした変化は、決して「自分がぶれている」ことではなく、むしろ自然な成長の証なのです。
人は一生、同じ姿のままでいられるものではありません。毎年、あるいは日々の中でさえ、新しい学びや体験を通して、違う自分に生まれ変わっていきます。大
切なのは、その変化を恐れずに受け入れることです。
過去の自分に縛られるのではなく、未来に向かって柔軟に歩み続けること。それこそが、人生を豊かにしていく力になるのだと思います。Have a nice day!!
げんき第12課「病気」|オンライン授業での展開例と教案
第12課「病気」では、学習者が日常生活で頻繁に遭遇する体調や健康に関するやりとりを学びます。日本語を学ぶ外国人にとって、医者に症状を伝えたり、友人に体調不良を説明したりするスキルは非常に実用的です。
本課では「~んです」「~すぎる」「~ほうがいいです」「~ので」「~なければいけません/~なきゃいけません」「~でしょうか」といった、説明・助言・理由提示・義務・確認の表現を身につけます。オンライン授業では、医者と患者のロールプレイや、生活習慣に関する助言のやりとりを組み込むことで、学習者が自然な会話運用力を伸ばせるように設計すると効果的です。
話題導入 / 語彙導入
授業の始まりでは、学習者が実生活に結びつけて想像しやすい「病気や体調不良」に関する語彙を導入することが効果的です。
まず画面共有でイラストやフラッシュカードを提示し、「あたまがいたい」「おなかがいたい」「のどがいたい」「ねつがある」「かぜをひく」などの基本語彙を紹介します。導入時には、教師が大げさに頭を押さえるジェスチャーをしたり、咳をする真似をするなどして、学習者が日本語を推測できるように促します。
例えば教師が画面上で自分の頭を押さえながら「いたい、あたまがいたいです」と言うと、学習者はすぐに理解しやすくなります。
そのあと学習者自身に「おなかがいたい」とジェスチャーをしてもらうなど、ロールプレイ的に練習させると、自然に語彙が定着していきます。
さらに、「どこがいたいですか」という質問を教師が投げかけ、学習者に「のどがいたいです」「せなかがいたいです」と答えさせる流れに発展させると、次の文型導入につなげやすくなります。
文型導入(場面提示 → 文型提示 → 文型練習)
ここでは第12課の中心的な文型を順に導入していきます。場面設定を用い、自然な会話の中で文型を提示することを意識します。
文型1「~んです」
場面提示:学生が授業に遅れてきました。教師が「どうしたんですか」と質問。学生役が「バスが来なかったんです」と答える。
文型提示:「~んです」は理由や事情を説明するときに使う。
練習:教師が症状を言い、学習者が「~んです」で説明する。
教師「おなかが痛いです」 学習者「食べすぎたんです」
まず「~んです」。教師は「どうしましたか」と学習者に問いかけます。学習者が「あたまがいたいです」と答えたら、教師が「そうですか。あたまがいたいんですか」と言い直して、文型を提示します。ここで「んです」は理由や状況の説明をするときに使うと説明します。教師自身が「きのう、ねつがあったんです」と例を示し、学習者にも自分の体調について「のどがいたいんです」「ゆうべねむれなかったんです」と言わせるように練習します。
文型2「~すぎる」
場面提示:学習者がカフェでケーキを三つ食べる写真を見せる。
文型提示:「~すぎる」は度を越していることを表す。
練習:教師「ケーキを三つ食べました」 学習者「食べすぎました」
次に「~すぎる」。教師が「このくすりはつよすぎます」「たべすぎました」と例を示し、学習者にイラストを見せながら「やさいをたべすぎました」「ねすぎました」と言わせます。健康に関する表現と組み合わせるとより実用的になります。
文型3「~ほうがいいです」
場面提示:学習者が風邪をひいている写真を提示。
文型提示:「~ほうがいいです」は助言をするときに使う。
練習:教師「熱があります」 学習者「病院に行ったほうがいいです」
続いて「~ほうがいいです」。教師が「ねつがあるときは、やすんだほうがいいです」と例を出します。その後「のどがいたいときは?」「かぜのときは?」と質問を投げかけ、学習者が「くすりをのんだほうがいいです」「たばこをすわないほうがいいです」と答える練習に発展させます。
文型4「~ので」
場面提示:学習者が「熱があるので、学校を休みます」と発言。
文型提示:「~ので」は理由を柔らかく伝える。
練習:教師が症状を提示し、学習者が「~ので」で理由を作る。
「~ので」は理由表現として導入します。教師が「きのう、あめだったので、でかけませんでした」と提示したうえで、「ねつがあるので、がっこうをやすみます」と病気に関連した例文を学習者に作らせます。
文型5「~なければいけません/~なきゃいけません」
場面提示:医者が患者に「薬を飲まなければいけません」と助言。
文型提示:義務や必要性を伝える表現。
練習:教師「熱があります」 学習者「薬を飲まなきゃいけません」
「~なければいけません/~なきゃいけません」は義務表現として提示します。「びょういんにいかなければいけません」「くすりをのまなきゃいけません」など、医者のアドバイスを想定したロールプレイを交えると自然に理解できます。
文型6「~でしょうか」
場面提示:患者が「この薬は毎日飲まなければいけないでしょうか」と医者に質問。
文型提示:丁寧に質問や確認をするときに使う。
練習:学習者が医者役に質問を作る。
最後に「~でしょうか」。これは丁寧に質問をするときに使える表現です。教師が「すみません、くすりはどのくらいのめばいいでしょうか」と例を示し、学習者にも薬局や病院で尋ねる場面を演じてもらいます。
ドリル(練習)
単文の練習からロールプレイに発展させる流れが有効です。
ここでは各文型を短い会話の中で繰り返し練習します。まずパターンプラクティスとして、教師が状況を提示し、学習者に即座に応答させる方式を取ります。
例えば教師が「きのう、ケーキをたくさんたべました」と言ったら、学習者は「たべすぎましたね」と返します。教師が「ねつがあります」と言えば、学習者は「びょういんにいったほうがいいです」と答える練習をします。このように、教師の台詞を手がかりに学習者が習った文型を用いて返答する形にすると、即応力が身につきます。
また「~なければいけません」と「~なきゃいけません」を交互に使わせる練習も効果的です。教師が「かぜのとき、なにをしなければいけませんか」と質問し、学習者が「やすまなければいけません」と答えます。その後で「じゃあ、くだものをたべなきゃいけませんか」と問いかけ、自然に「はい、たべなきゃいけません」や「いいえ、たべなくてもいいです」と応答させます。
ペアワークとして「病院の医者」と「患者」の役割を交代しながら練習するのも良い方法です。患者が「のどがいたいんです」と説明し、医者役の学習者が「このくすりをのんだほうがいいです」「あしたまたびょういんにこなければいけません」と助言する形で文型を活用します。
単文の練習からロールプレイに発展させる流れが有効です。
・症状→助言
教師が「のどが痛いです」と言い、学習者が「薬を飲んだほうがいいです」と答える。
・度を越す行動→「~すぎる」
教師「コーヒーを五杯飲みました」 学習者「飲みすぎました」
・理由説明→「~ので」
教師「今日は雨です」 学習者「雨なので、外に出ません」
・義務確認
教師「この薬は一日三回です」 学習者「一日三回飲まなければいけません」
ドリルはテンポよく行い、発話量を確保します。Zoomならブレイクアウトルームでペアに分けて行い、短い時間で多くの練習ができるようにします。
談話練習(ディスコース練習)
談話練習では、学習者が習った文型を組み合わせて、より長い会話を構築できるようにします。ここでは「病気で学校や会社を休む」「病院に行って診察を受ける」「友達に体調を相談する」といった具体的な場面設定を用いると効果的です。
例えば「病院の受付で会話をする」活動を設定します。学習者Aが受付役で「どうしましたか」と聞き、学習者Bが「きのうからおなかがいたいんです」と説明します。受付役は「そうですか。おいしゃさんにみてもらったほうがいいです」と応じ、その後で「このけんさはいたいでしょうか」と尋ねる流れにします。
別の活動では「友達との会話」を設定します。学習者Aが「かぜをひいたんです」と話し、学習者Bが「じゃあ、きょうはうちでやすんだほうがいいです」「くすりをのまなきゃいけませんよ」と助言します。そのあと学習者Aが「わかりました。でもしゅくだいをしなければいけません」と返し、自然なやり取りにつなげます。
このように「~んです」で状況を説明し、「~すぎる」「~ほうがいいです」「~なければいけません」「~でしょうか」を組み合わせて応答させると、学習者は実際の生活場面に即した会話力を養うことができます。
談話練習では文型を組み合わせて、より自然なやりとりを体験させます。
事例1 医者と患者のロールプレイ
患者「先生、頭が痛いんです」
医者「そうですか。熱はありますか」
患者「少しあります」
医者「薬を飲んだほうがいいですよ。毎日三回飲まなければいけません」
患者「寝てもいいでしょうか」
医者「ええ、ゆっくり休んでください」
事例2 友達との会話
A「顔が赤いね。どうしたんですか」
B「昨日、飲みすぎたんです」
A「そうですか。今日は早く寝たほうがいいですよ」
B「はい、そうします」
このように複数の文型を組み合わせて状況を完結させることが、学習者の会話力を伸ばす鍵です。
授業の最後には「今日学んだ文型を使って、自分の体調や健康習慣について1分話してください」とまとめ発表をすると定着が高まります。
事前登録を受付中!Manabi Talkについて
「Manabi Talk」は国内運営のオンライン日本語学習プラットフォームです。学習者は安心して日本語を学べ、教師は自由に授業スタイルを設計できます。今回紹介した第12課「病気」の教案も、実際にプラットフォーム上で活用可能です。
体調や健康は誰もが関わるテーマであり、学習者の生活に直結した学びになります。
授業後に「またManabi Talkで予約して学びたい」と思ってもらえるよう、会話の達成感を重視することがポイントです。
Manabi Talkは、オンラインで日本語を教えたい講師と、学びたい外国人学習者をつなぐ新しいプラットフォームです。初めて授業を行う新人講師でも、安心してスタートできるよう、教案テンプレートやフォロー体制を整えています。
「これから日本語教師として実践を重ねたい」「でもいきなり大きな現場は不安…」という方にとって、Manabi Talkは実力を磨くための第一歩になるかもしれません。
現在、Manabi Talkではユーザー登録および講師登録を受付中です。ぜひこの機会に、あなたも新たな挑戦を始めてみませんか?
Manabi-talk LP:https://manabi-talk.net/lp

まとめ
在宅で働けるオンライン授業は、日本語教師にとって新しい収入の道を開くチャンスです。
これからは、「教室」だけでなく、「自宅」も立派な教える場となる時代。
ぜひ、オンラインで活躍する日本語教師もお考え下さい!オンライン講師への本登録は8月下旬より可能となります。
それまでのプレ登録をして頂ける方を募集しております。講師様お一人お一人に管理画面をご利用いただけます。8/25(月)を目指して現在開発中です。