会話中心の導入法とは?オンライン授業で『げんき』を活用する方法シリーズ
こんにちは。8月4日の月曜日です。昨日、一昨日の記事更新ができませんでした。ですが昨日は昨日と思い進んでいけば、きっとより良い方向に向かえるはず。今週も変わらず、Manabi Talkをより多くの方々に知って頂けるように準備を重ねていきたいと思います。
今日の元気ワード〜昨日は昨日、今日は今日〜
昨日、うまくいかなかったこと。
悩みすぎて眠れなかった夜。
やる気が出なくて、自分を責めてしまった気持ち。
でもね、昨日はもう過ぎた日。
どんなに思い返しても、やり直すことはできないけれど、
そのかわり、今日という一日がまた目の前にあるんです。
「昨日は昨日、今日は今日」って思えるだけで、
心に少しだけ余裕が生まれます。
あきらめなくていい、立ち止まってもいい。
ただ、また一歩だけ前に進めば、それでじゅうぶん。
人生は毎日が更新の連続。
昨日の自分に縛られず、今日の自分がどうしたいかを大切にできれば、
きっとまた先に進む力が湧いてきます。
落ち込む日があってもいい。大丈夫。
今日もあなたのペースで、一歩ずつ、歩いていきましょう。
その一歩は、昨日とは違う未来につながっていますから。
それでは今日も引き続き、「げんき」を利用したオンライン授業特集を行っていきたいと思います。
なぜ「会話中心の導入」が注目されているのか?
オンライン授業が普及し、「教科書通りに進めるだけでは、学習者の発話が増えない」という悩みが多くの教師から聞かれるようになってきました。
特に『げんき』シリーズのような定評ある教材を活用する中でも、「文法や語彙の理解だけで終わってしまう」「会話練習が後回しになってしまう」という問題がしばしば起こります。
そこで、注目されているのが“会話中心の導入法”です。
この方法は、文法や語彙をただ教えるのではなく、「実際の会話の中で自然に導入する」アプローチ。
つまり、教える内容がそのまま会話につながる構成を意識して授業を設計することで、学習者の発話量が増え、日本語の定着も高まるのです。
今回は『げんき』を使った授業において、会話中心の導入がどのように機能するのか、その実例とともにご紹介していきます。
なぜ会話からスタートするのか?──自然な「使える日本語」習得の第一歩
多くの初級者は、日本語を「正しく話す」ことに集中するあまり、実際の場面で言葉が出てこないという壁にぶつかります。
これを乗り越えるには、文法や語彙の習得を先に行うよりも、「その言葉がどう使われるか」をまず感じ取ることが重要です。
これが、会話を起点にする導入の効果的な理由です。
例えば『げんきI』第6課で「〜てください(please do)」を導入する場合、いきなり「命令の丁寧形です」と説明するのではなく、以下のようなやり取りから始めると、学習者は「実際の会話の中でどう使うのか」が直感的に理解できます。
👩🏫 教師:「はい、ドアを閉めてください」
👨🎓 学習者:(動作をしながら)「あ、OK…ドアを閉める、ですね」
👩🏫 教師:「Yes! '閉めてください' means 'Please close it.'」
👩🏫教師:「今日の午後、映画を見に行きませんか?」
👨🎓学習者:「え?行きませんか?」(少し混乱)
👩🏫教師:「Yes! It's an invitation. I’m inviting you.」と笑顔で説明。
このような体験ベースの理解は、学習者にとって記憶にも残りやすく、定着率も高まります。
日本語が「教科書の中の文字」から「実際に使う言葉」へと変わることで、学習に対するモチベーションも高まるのです。
会話中心の導入を成功させる3つのポイント
1. シチュエーションに基づいた導入
事前に用意したシナリオ(例:駅で道を聞く/友達を誘う/買い物をする)に基づいて文型を自然に出すと、学習者は文型を“目的のある表現”として捉えることができます。
例えば「〜ませんか?」の導入では、
👩🏫 教師:「あした一緒にお昼を食べませんか?」
👨🎓 学習者:「はい!行きましょう!」
👩🏫 教師:「Great! So ‘〜ませんか’ is how we invite someone.」
というように、使いながら文型を理解していく流れが効果的です。
2. “Yes/No”で答えられる簡単な質問から始める
初級者は自信がないため、最初から自由回答を求めると緊張してしまいます。まずは「〜ですね?」「〜ですか?」といった確認型の会話で安心感を与えるのがコツです。
👩🏫「これはパンですね?」
👨🎓「はい、パンです!」
👩🏫「おいしいですか?」
👨🎓「はい、おいしいです!」
このように、「分かる」「使える」という成功体験を積ませることが、自然な会話につながる第一歩になります。
3. リアクションとフィードバックを忘れずに
会話の中で正解・不正解をすぐに判断せず、フィードバックを“賞賛型”で返すことで、学習者は安心して話すことができます。
👨🎓「わたし、昨日、ラーメン、たべました」
👩🏫「Great! ‘たべました’ – perfect past tense! Excellent!」
こうしたフィードバックの積み重ねが、学習者の発話への自信を支え、さらに積極的な会話参加へとつながります。
実際のオンライン授業での活用例と学習者の反応
会話導入型の授業を実施した講師たちからは、非常にポジティブな反応が報告されています。
例えば、ある教師は『げんき』第7課の「〜ています(ongoing action)」の導入を以下のように実施しました。
👩🏫 教師:Zoomでビデオをオンにしながら、「今、何をしていますか?」
👨🎓 学習者:「えーと、話しています!」
👩🏫 教師:「Yes! You are talking now! So, ‘話しています’ is present continuous.」
ここで“grammar explanation”に入る前に、学習者は自分の行動を日本語で言うことに成功したという自信を持てたのです。続けて「今、誰と話していますか?」などの応用質問を重ねることで、文型の運用力が深まりました。
また、受講した学習者からは以下のような感想がありました:
- 「いつも会話から始まるので楽しい」
- 「説明よりも先に“わかる”気がして、緊張しない」
- 「すぐに使いたくなる表現が多くて実用的」
これは、“文法の理解”よりも“使える日本語の体得”を優先するManabi Talkの授業スタイルが、学習者にフィットしている証拠と言えるでしょう。
Manabi Talkだからこそできる会話中心の個別レッスン
Manabi Talkでは、1対1のマンツーマンレッスン形式を採用しているため、
学習者のペースや興味に合わせて自由に会話を展開できるのが特長です。
たとえば同じ文型でも、ある学習者には「仕事の話題」で、別の学習者には「アニメの話題」で導入するなど、柔軟なアプローチが可能です。
さらに、『げんき』のような教科書をベースにしつつ、学習者の背景に合わせた“実用会話”を織り交ぜることができるのもマンツーマンの強み。
文法中心の座学ではなく、“話すための日本語”を最初から意識する授業づくりが、学習の持続力や成果に直結しています。
事前登録いよいよスタート!Manabi Talkについて
Manabi Talkは、オンラインで日本語を教えたい講師と、学びたい外国人学習者をつなぐ新しいプラットフォームです。初めて授業を行う新人講師でも、安心してスタートできるよう、教案テンプレートやフォロー体制を整えています。
Cさんのように、「これから日本語教師として実践を重ねたい」「でもいきなり大きな現場は不安…」という方にとって、Manabi Talkは実力を磨くための第一歩になるかもしれません。
現在、Manabi Talkではユーザー登録および講師登録を受付中です。ぜひこの機会に、あなたも新たな挑戦を始めてみませんか?
Manabi-talk LP:https://manabi-talk.net/lp

まとめ
在宅で働けるオンライン授業は、日本語教師にとって新しい収入の道を開くチャンスです。
これからは、「教室」だけでなく、「自宅」も立派な教える場となる時代。
ぜひ、オンラインで活躍する日本語教師もお考え下さい!オンライン講師への本登録は8月下旬より可能となります。
それまでのプレ登録をして頂ける方を募集しております。講師様お一人お一人に管理画面をご利用いただけます。8/6(水)を目安に現在開発中です。

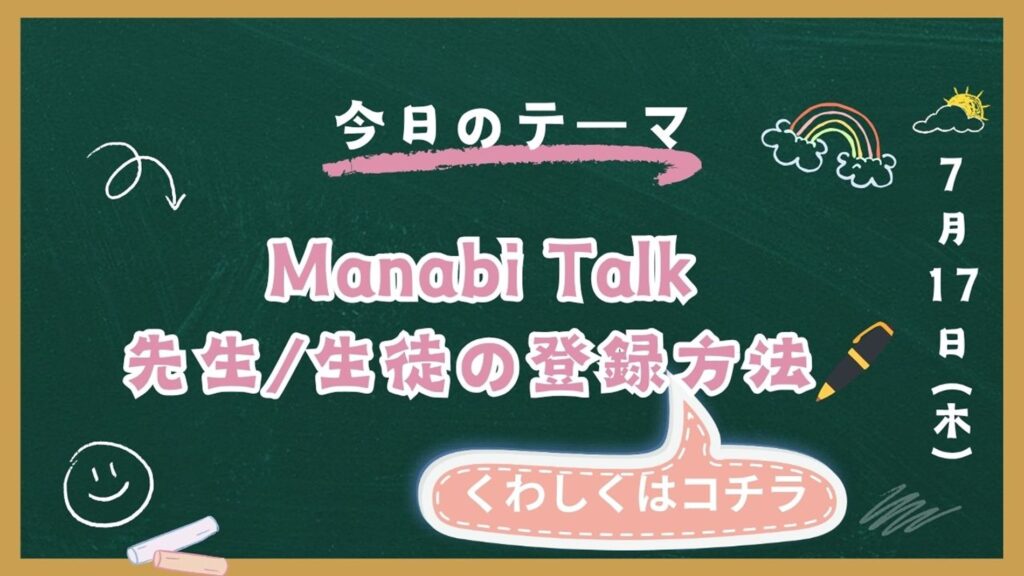

現在、8月末までにお申し込みを頂くと
①オンライン授業で使える教案例集プレゼント(3点セット)
②手数料を半年間、5%割引キャンペーン 15%→10% を実施します。
尚、Xのフォローもして頂けると嬉しいです*^^*
